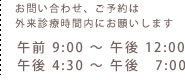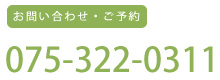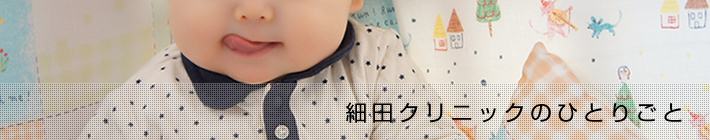ブログに書くかやめようか悩んだ末、書くことにした。
タイトルの通り、すごく悔しく、悲しかったできごと、腹が立ったこと。
昨日の出来事だ。
午前中、外来を済ませ、昼から銀行、社会保険や国保に出し物があり、かつ、3時にはクリニックに戻らなければならなかった。同時に行動するため、院長と私二人で行動した。
すべて用事をすませ、クリニックに帰る車の中。
私は2夜連続徹夜のため、車の助手席でウトウトしていた。
そんな中、主人が、「クリニックから電話だ」と言いながら、携帯を手にしていた。
「もしもし、うん、うん・・・・」
と言いながら、左車線に車を止めようとしたその瞬間、警察の「ピピピ・・・」という笛の音でわき道に誘導されてしまった。
つまり、運転中に携帯使用でつかまってしまった訳だ。
ほとんど運転中にある着信は私が主人の携帯をとることも多いが、そのときは主人が携帯を開いた。携帯に表示される「クリニック」という文字を見た瞬間、路肩に車を寄せ話をした、その一瞬であった。
4~5人の警官が車を取り囲む。
そこからの会話が、下記の通り。
警察・・・「(手柄のように)はい、おたく携帯使いましたね。携帯を使いながら、30m走行しましたね!まちがいないですね!」
院長・・・「はい、でも、道の脇に止める1.2秒ですよ」
警察・・・「それでも規則は規則。はい、免許証出して」
院長・・・(財布から免許証を出しながら)「あ~あ、やられた。」
私・・・「あの~、産婦人科のクリニックの院長をしていて、クリニックから電話があれば、何よりも患者さんの命の責任があるのです。家族や友人からの電話は出ませんが、クリニックということが判れば、一刻を争うかもしれないから、出ないわけにはいかないのです。もちろん、車を端に寄せようとしましたよ。そのことはわかってもらえないですか?」
警察・・・「理由がなにであっても、規則は規則。産婦人科の医師であっても携帯を握って車乗らないでくださいね。かかってくるとわかっていたら車は乗らないでおいたらどうですか?」
私・・・(もう怒り↑↑)「ありえない。訳判らん!!もう、話にならない!世間で産婦人科医がいなくて、妊婦さんがたらいまわし・・というニュース知っているでしょ?そこまで、産婦人科が大変で一刻を争うことということを知ってはるでしょ?電話の対応が数分遅れたら、赤ちゃんの命、お母さんの命が危ないこともあるのですよ。そのことは判ってもらえますか?そちらの家族が妊婦さんだったらどうです?何ですぐに先生と連絡取れないんだ!と怒るでしょ!!」
警察・・・「それはまた別の問題で・・まあまあ・・」
私・・・「別じゃないですよ!!同じじゃないですか。何回も言うけど産婦人科では1分が命取りになることがあるんですよ。」
警察・・・「じゃ、クリニックから電話があったら、となりにいる奥さんが電話出ればいいじゃないの↑。あとでかけ直すとか、用件聞くとか・・」
私「だから、言ってるじゃないですか。1分を争うことあるって。だれも、携帯かけながら堂々と走行してるわけじゃないでしょ。クリニックをいう表示を見て、車を止める1、2秒を理解して欲しいだけなのに・・」
警察「事情は何であれ、ダメなものはダメ。メールもダメでしょ。知ってるでしょ?だから、携帯を手に持ってみることもダメに決まってるじゃないですか。わかります?・・で、印鑑もってますか?それから職業は?」
私「そんなの印鑑常時持ってるわけないでしょ!!!それに、こんなに話していて、職業は?はないでしょう。業務的過ぎませんか?」
こんな会話を数分。
携帯を使用しながらの車の運転は理由は何であれダメなことはわかっている。
しかし、捕まえて罰金取ることを手柄のように対応され、産婦人科のことを何一つわかってもらえなかったこと、自分の家族だったら別の問題といったこと、話にならなかった。更に、私の気分を悪くしたこと。
それは以前ブログにも書いたことがる。警察の方が、うちのクリニックの駐車場に不法駐車をしていたことがある。
1回目は、クリニックの近くで事故があり、その現場検証するために乗ってきた車を止めるところをどこにしようか、と見渡したら、クリニックの駐車場が空いていたので、という理由でパトカーを止めていたこと。そのときは、クリニックで何かあったのか、と驚く私たちの前で「すいません、何だったら移動させましょうか?」と言われたので、「別にいいですけど、緊急じゃなかったら一言クリニックに電話入れてください。今日はこのままとめておいてもらっていいです。」と譲ってしまったこと。
2回目は、五条通りを走る不法な車両をビデオ撮影するのにクリニックの駐車場が撮影場所に絶好だったから、と勝手に覆面パトカーを駐車していた。そのとき来られた患者さん何人もの方が不審に思い、怖い思いをされたこと。そりゃそうだ。大きな男性の方がクリニックの駐車場で車の中からビデオを撮影し、それを取り囲んで話をしている。しかも産婦人科の駐車場で。患者さまが変な車が止まっています、言いに来られ、すぐ110番しようか、と思ったが、勇敢なスタッフが直接その男性数人に、お宅ら誰?と聞いてくれて、警察の人とわかった。
そのときも、警察の方は「すいません・・、ここが一番ビデオ撮影に良かった場所だったので・・もう、終わりますね~」と軽く済んでしまった。
その2回の出来事を思い出し、警察の方の行動は不法駐車という規則違反しても「仕事だから」で済まされて、今回、命のかかっている産婦人科の立場を全く理解してもらえなかったことに怒りが爆発してしまった。
帰りの車で、「そんな罰金払わなくていいよ。」と言う私に、院長は「でもな、払わなかったら警察の指示した日にお産があろうと外来の日であろうと出頭しないといけないんや。そしたらもっとたくさんの人に迷惑かかるやん。むっちゃ腹が立つけど払うしかないんや。」
と。
たかが携帯一つ、と思いきや、お風呂のときもトイレのときも、私も院長も半径2mくらいにおいておかなければならない現実。警察の方みんながそうとは思っていないが、少しは産婦人科の中身を知って欲しいと強く思うと同時に、運転しながら平気で携帯しながら赤信号でも突っ込んでくるトラック、夜中にプーパープーパー鳴らしながら列を作って走るバイク、それらをしっかり取り締まって欲しいものだ。
私の怒りは優しいスタッフが、「フンフン」と聞いてくれ、いっしょに怒ってくれて少しは治まったが・・・・ブログに書いて更に自分を落ち着かせてみた
。
eri.hosoda
歩くこと
最近、院長やスタッフが感じることは、初めてのお産の方がとても安産なことだ。
経産婦さんは、お一人、もしくは、お二人、生んでおられるから時間的に見たらそんなにかからない。
初めてのお産の方は、教科書には「12~14時間」というのが平均とされている。
細田クリニックでお産をされる初めての方の平均は、ざっくりではあるが、平均してみたら、7~8時間前後である。
特別な指導や教室はしていない。母親教室で、なぜ、歩くことが大切なのか、体重制限が大切なのかはお話し、毎回の妊婦健診では、妊婦さん本人だけでなく、いっしょに来られるご主人にもその必要性を説明、話をする。
それだけであるが、ほとんどの方が体重制限をがんばって、さらに、院長の
「とにかく歩きなさいね~」の言葉を守って信じてくださっている。
本当にそれだけ。
もちろん、がんばって体重増加を抑えて、毎日歩いていたとしても、分娩時間がかかったり、骨盤より赤ちゃんの方が大きく帝王切開になったり・・ということは、避けられない。他の状態も踏まえて緊急事態ということはゼロではない。皆さん確立はあるわけである。元気に「オギャーと泣いてもらうことが第一」それが基本である。
ということは、赤ちゃんにもお母さんにもストレスがかからない、というのがベストである。そうすれば、育児にスムーズに入っていけると思う。
昨日お産された方は、超が10個くらいつく程安産。破水されて来院、その頃より陣痛が来て、1時間でお産をされた。元気な真ん丸い女の子を素敵な素敵なお父さんに見守られて生まれてきた。
お産のあとの笑い話であったが、破水で入院、となると、分娩まで時間がかかるから、お茶とストローと用意して、がんばって呼吸法をやろうと意気込んでこられたそうだ。とりあえず病院に向かおう、落ち着いた頃に、カメラやビデオを取りに帰ればいいか、と考えていたそうだ。それが、お茶も飲む暇なく、いきむこともなく出産!
この前無事退院された方も、ご主人がまだ職場だったため、とりあえず、産婦さんだけクリニックに来られた。ご主人もクリニックに向かっておられるはずだが、お産の進行が早く、夜中だから道も空いているはずなのに、ご主人、間に合うかどうか・・という状況。ご主人が到着、その何分か後に出産!
お母さんがご主人に向かって「来るのが遅いよ~(笑)」
すかさずご主人「お産が早すぎるよ~(笑)、お茶くらい持っていってやろうと思いとりに帰ってたのに分娩室でお茶をカバンから出す時間もなかったわ。」
そりゃそうだ。入院して1時間少し。ご主人の発言が正解!
どの方も、いいお産をするために、赤ちゃんにストレスをかけないように、時間をかけずにお産できるように、と、がんばってがんばって歩いておられる。もちろん体重も増やさず・・。
朝の涼しいうちに、と6時に起きて西京極公園を歩いておられる方もあった。本当に脱帽である。
すごく原始的で自然なことであるが、とにかく「歩く」ということが一番の安産への近道なのかもしれない。
eri.hosoda
辞任
世間は安倍首相が突然辞任し、新聞やニュースでトップニュースで取り上げられている。
それは、私たち庶民には、テレビの中の出来事ではあるが、安倍首相が辞任と速報されれば、なぜ突然辞任?次期首相は誰?とあらゆる角度から報道され、それを元に庶民も、話のねたになっている。
国家の主が辞任、大きな出来事であるが、どんな理由であっても辞任が出来る。
院長は???
心身とも疲れたから辞めます・・・
なんてことは、絶対無理な話。
もし、今月いっぱいで辞めます、と発表したらどうなるのだろうか。
たくさんの患者さまは、命を託してくださってるのだから大迷惑だろう。
何人ものスタッフが、細田クリニックで働いてくれている。私達どうなるの?と混乱が生じること間違いない。
でも、世間の産婦人科はドンドン閉鎖されていく状態。外来はやりますが、入院施設は閉鎖します、という開業医もある。
さらに、産婦人科医になりたい、という医学生も減る一方。
よって、ますます、産婦人科の置かれる状況は悪化する。
院長は、ある程度の年齢で自分のフェイドアウトを決めなくては・・と考えている。
産婦人科医は昼夜関係なく、365日拘束がある。そのストレスの中でがんばれるのは今の年齢がピークで老年期になれば、誰でも体力は絶対落ちてくる。目や手先に年齢は現れてくる。その中で、命を預けに来てくださる患者さま、妊婦さまには申し訳ない。
2年前、開業するに当たり、全国の多くの産婦人科&他科の開業医の先生に勉強させていただく意味で、お話を聞かせていただいた。
お産をたくさん受けておられる先生も、65歳くらいできっぱり辞めますよ、と話しておられた。
また、定年は無いが、末永く心身とも健康で仕事が続けられるように、一ヶ月に数日は他の先生にクリニックをお願いして、全く携帯を気にせず、一人のおじさんとして街を歩くようにしています、と言われていた先生もおられた。
どこの産婦人科の先生も、静かな田舎の先生も、東京の真ん中でやっておられる先生も、みんなこれからの産婦人科医の寿命について考えておられた。
首相のように、「続投します、いや、やはり、辞任します、食欲がなく疲れたから入院します」と簡単に出来ない院長の立場。
考えようによっては、首相よりしんどいかも???
eri.hosoda
世界陸上
数日前から、大阪で世界のトップアスリートが競っている。
暑い日本での競技はさすがの世界レベルの人たちでも、堪えているらしい。
観戦に行っている人々も大変だろう。
出場している選手の家族やチームメートはわかるが、全く関係のない人たちは、滅多にない世界のトップを目の前で見る、ということを味わいに行っているのだろう。
ルールやその競技の良し悪しは知らないが、世界一の100mの走りや、世界一の高飛び、目の前で見たらどんな感激なんだろうか。
テレビで見ているだけでも、足が細く、長く、その選手の一歩が私の三歩ほどありそうな外人さんを見ていたら、日本人と違うなあ~と思う。
スポーツに限らず、今まで、世界のトップレベル・・・というものを肉眼で見たことがあるだろうか・・。どれだけ思い起こしても、思い浮かばない。
世界のスポーツ選手・・・みたことない・・。
世界の首脳陣・・・テレビでしかない・・。
世界共通のミュージシャン・・・名前も知らない・・。
世界一の何かを見たら絶対自分の中の価値観が変わると思う。
私たちの生活では、日々出産という感動はあるが、それとは全然違うまた別の感動があるはずだ。
自分の好きなコンサートに行く、見たい映画を見る、それも、感動であろうが、全く知らない何かの世界一を見ることも体験してみたい。
もし、本当に、もしも・・、だが、クリニックに<世界>とまではいかなくても、<世間>で名の通った方が受診に来られたら、ずっと連絡が取り合えるお近づきになりたい。
むちゃくちゃ、ミーハー?!だ。でも、最初は、きっと、しゃべれなくて、スタッフに、「一緒に来てしゃべって~お願い!」と言いそうだ。
今、思い出した。
友人のご主人は、ノーベル賞をもらった島津製作所の田中耕一さんと同じ部署で机を並べて仕事をしていたらしく、それまでは、普通の同僚だったのに、職場にいる本人に直接ノーベル賞の受賞報告の電話がかかってきたらしい。(~本当に、その場にいたそうです~)、こんなに感動したことないくらい、まるで自分のことのように感動して家族に電話したそうだ。今まで普通に隣で話してた人が、その電話一本で世界の人になった瞬間、そんな体験、そう簡単にありえない。
eri.hosoda
夏
お盆も過ぎ、8月の後半に突入した。
この平成の時代、お盆が過ぎても、35度!常夏のハワイやグアムの方が体感温度は涼しいであろう。
今生まれた子供たちが成長し、大人になったとき、今とはまた違う夏を体験するのであろう。
気温・・もっと上がるのか??
9月どころか、10月でも30度以上あるのか??
夏の平均気温40度も当たり前になるのか??
熱中症防止に、外にはでない生活になるのであろうか??
暑さで野菜が育たず、生産がドンと減ってしまい、食生活が変わるのか??
高校野球も暑さで中止になる??
外出禁止令がでるのでは??
そんな、バカな・・と思ってしまうが、私たちの子供のころ、熱中症で人が死ぬなんてありえなかった。真夏でも思いっきり外で遊んでいた。朝は涼しいから、朝のうちに宿題をしなさい、といわれていたくらい、朝のうちは、扇風機だけで充分しのげた。クーラーのない家もたくさんあった。お盆が過ぎたら、浜辺はひっそりとし、泳ぐ人はいなかった。
それが、20年30年たった今は、想像もしていなかった世の中になっている。
人間が作り出す物は、変化することは当たり前であるが、自然まで変化することが怖くも思う。
2030年、2040年、その頃、私たちの世代は、元気であれば、人生の後半を生きている。
どんな夏をすごしているのだろう。
私、耐えられるであろうか?
そして、今生まれた子供たちが、大人になって、その夏をどう生活しているのか、大げさに言えば、想像もできない日本の夏を、どう生きていってくれるのか・・・。
考えると、一瞬、怖くなる。しかし、避けてはいけない問題として真剣に考えなくてはいけないのだろう。
eri.hosoda