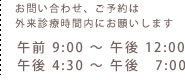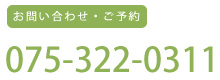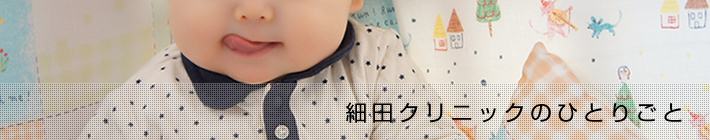外来が休みの日には、用事、気分転換に、いろんなところに出かけることが多いです。
もちろん、何かあればクリニックに戻れる距離限定ですけれど・・。
いろんなところに出没する私たち・・だから、いろんな方にお会いします。
二条にあるBivi、用事で近くに行き本屋さんへ立ち寄った数分・・妊婦さんのご主人に声かけられました。その近くでランチをしたら、向かいの席にはお産された方。
伊勢丹で買い物・・レジの方に「先生ですよね」と言われました。
子どもの用事で四条の寺町・・はぐれそうになるほどの人ごみの中、出産された方とぶつかりました。お互い「いや~こんなところで・・」と笑顔で一瞬の会話。
オープン早々のヨドバシカメラ・・よく覚えているご家族に遠くから会釈されました。そうそう、ヨドバシカメラだけで5人くらい患者さまを見かけました。
阪急電車に一駅乗っても、たまたま前に立たれた方が、最近お産された方。
バスに乗り遅れそうで、バス停に走っていく姿をお産された方に「お出かけですか?」と手を振って声かけられたり・・。
近くのユニクロ・・ご家族で買い物中に声をかけてくださり、抱っこさせてもらいました。
高島屋で・・大丸で・・、言うまでもなく、近くのライフ、マツモト、京ファミ、洛南ジャスコ・・。そうそう、ヤマダ電機では、必ずと言っていいくらい、お二人くらいはお会いします。・・ローカルな話ですいません。
もちろん、スタッフもよく患者さまをお見かけするようです。
同じマンションとか、たまたま入ったラーメン屋さんとか、京タンス、ハナ、学校、などなど。仕事中は髪の毛をくくって白衣、でも、街では髪形も変え、私服なのに、患者様のほうから声をかけてくださるので、驚いたこともあるようです。それは、すごくうれしいこと、ありがたいことです。
声かけてくださったり、遠くから会釈してくださり、抱っこされている赤ちゃんを指差して「この子この子・・」と笑顔でジェスチャーしてくださったり・・。
その都度、あの方のお産は真夜中だったなあ・・とか、あそこのご主人、すごく優しかった記憶・・とか、それぞれのお産のエピソード、断片的ですけど、記憶をたどることができます。
でも、お名前が出てこなかったり、何年前だったか、という記憶がなかったり、ということもしばしば。
そんなときは、お名前をお聞きすることもあるかと思います。そうすれば、消えない記憶として学習しますので、よろしかったら教えてください。
スタッフも同じだそうで「お顔はよく覚えているんですけど、お名前お聞きしていいですか・・」と聞くのだそうです。
地域に根ざしたクリニック。
5年経てば、お会いする方も増えてきます。
すごく、うれしいです。
疲れていても、タラタラ歩いてられませんよね。
汚い姿で、歩いてられませんよね。
常にほど良い緊張感を持ちながら、街に出ようと思います。
でも、もし、疲れた顔でボーと歩いていたら、渇を入れる意味で声をかけて下さい。うれしいです。
eri.hosoda